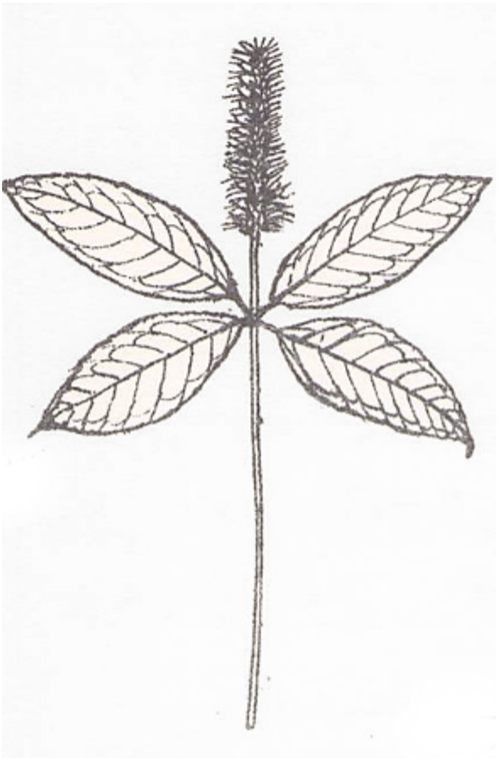松浦佐用彦
1856年豊永郷黒石に土佐藩士松浦家の長男として生誕。土佐藩の官費生として東京外国語学校に入学。卒業後、東京開成学校(現東京大学)に入学。佐々木忠次郎と共に理学部に進学し、東京大学動物学初代教授エドワード・S・モース(以下モース)の学生として研究をする。1877年8月植物学教授の矢田部良吉とその学生松村任三と共に江ノ島で臨海実験所を開設、貝等の標本採集を行う。同年9月16日モースは松浦佐用彦と佐々木忠次郎と大森貝塚発掘の下見に初めて出かける。10月9日矢田部良吉も同行し、本格的な調査が始まる。モースが不在の間、 大森貝塚発掘を松浦佐用彦と佐々木忠次郎が任され、12日間の調査を行っている。東京大学学報第6報でモースは調査と報告を称賛をしている。
モースは、チャールズ・R・ダーウィンの『種の起源』の進化論を初めて日本で講義をおこなった人物である。松浦佐用彦に『種の起源』アメリカ版第6版を最初に渡し、後に佐々木忠次郎、種田織三の所有となっている。モースは大森貝塚を発掘をすることで日本の近代の考古学や人類学に多くの影響を与えた。東京大学に進言し、研究報告書である大学紀要を日本で始めて発刊し、博物館を新設した。日本に滞在中は、日本人の生活に関心を持ち、多くのスケッチを描き、民具を収集し、アメリカのセイラム・ピーボディ―博物館に、世界有数のコレクションとして現在も日本の民具が収蔵されている。
松浦佐用彦は東京大学の地質学、動物学、人類学の学生が中心となり1878年2月に設立された「博物友会」の設立者の一人となっている。
1878年4月松浦佐用彦は病を患い、モースは時折見舞っている。同年7月5日、松浦佐用彦は、東京で没する。豊永郷黒石の実家に死亡通知を送ったが返事はなく、モースや学友達によって葬儀、埋葬が行われ東京の谷中霊園に埋葬された。墓石にはモースの言葉と学友で日本近代書道の父と称される日下部東作言葉が記されている。帰国前の1883年1月29日にエドワード・モースは佐用彦の墓所を訪れている。アメリカへの帰国後も講演で松浦佐用彦について語っている。またモースの著書『日本その日その日』では、松浦佐用彦について多くのページを割いている。1927年3月20日学友だった佐々木忠次郎達は、上野の精養軒で松浦佐用彦の50回忌追悼会を開き、多くの学友が集まったことが記録されている。
エドワード・S・モースが記した墓石文
A FAITHFUL STUDENT, A SINCERE
FRIEND, A LOVER OF NATURE,
HOLDING THE BELIFE THAT IN
MORAL AS WELL AS IN PHYSICAL
QUESTIONS “THE ULTIMATE COURT
OF APPEAL IS OBSERVATION AND
EXPERIMENT, AND NOT AUTHORITY”
SUCH WAS MATSURA.
EDWARD S. MORSE.
忠実な学徒にして誠実な友、自然を愛した人 倫理面だけでなく物理面の問題でも”最終的に判定をくだすのは権威ではなく、観察と実験である”という信念を抱いていた人 それが松浦だった
日下部東作が記した墓石文
松浦佐用彦墓碑銘
君姓松浦名佐用彦土佐人蚤入東京大学就莫爾斯 先生専攻生物之学研磨淬礪頗有所究明治十年 七月五日病疫而歿享年二十有二君性恬澹其待人粗不置藩垓故為衆所欣慕頃友人相謀建碑于天王寺之銘之曰 宿望未遂 凋落如花 吁嗟天道 是耶非耶
正五位日下部東作表題
東京大学有志輩建立
明治十二巳卯歳七月八日
彼の姓は松浦で名は佐与彦。土佐の産である。若くして学校に入り生物学の研究に身をゆだねた。精励して大きに進むところがあった。明治九年七月五日、年二十二歳、熱病で死んだ。彼の性質は明敏で人と差別をつけず交わったので、すべての者から敬慕された。彼の友人達が拠金してこの碑を建て、銘としてこれを書く。
胸に懐いていた望はまだ実現されず 彼は焇れた花のように倒れた
ああ自然の法則よ
これは正しいのか、これは誤っているのか
正五位日下部東作記 東京大学有志建 明治十二年七月八日